初心者でもわかる ダーツ講座/初心者編 おすすめのマイダーツ
| メニュー |
| トップページ |
| このサイト |
| ニュース |
| マイダーツ特集 |
| バレル |
| フライト |
| シャフト |
| チップ |
| ケース |
| ダーツボード |
| フライトパンチ |
| カード |
| アクセサリ・その他 |
| 初心者でもわかる ダーツ講座 |
| 基礎編 |
| 初心者編 |
| 中級者編 |
| 上級者編 |
| FAQ |
| 特設コーナー |
| 0円で節約上達生活! |
| 読書で上達生活! |
| パーツレビュー |
| コラム |
| ダーツライブを楽しむ |
| フェニックスを楽しむ |
| ダーツバー(カフェ) |
| ネットショップの攻略法 |
| オススメの動画 |
| 情報配信者様へ |
| ブログをはじめる |
| ホームページの素材 |
| ネットでダーツ代を稼ぐ |
| リンク |
| 情報サイト |
| 厳選ブログ |
| オススメショップ |
| その他 |
初心者でもわかる ダーツ講座/初心者編
ここは、初心者向けのダーツ講座です。
目安は、未経験者〜FLIGHT.CC程度を想定しています。
初心者におすすめのマイダーツ情報はこちらから。
>>..初心者におすすめのマイダーツ
ルール等、基本的な説明は『ダーツの基本』をご覧下さい。
>>..ダーツ講座 基礎編
初心者向けの具体的な練習方法はこちらから。
>>..初心者の練習法
ソフトダーツから始めよう
ダーツには、ソフトダーツとハードダーツがあります。まずは、比較的、多くのお店に出回っており、得点を電子計算してくれる便利なソフトダーツから始めましょう。
ダーツカードを入手しよう
ソフトダーツには大きく二種類のゲーム機があります。
ソフトダーツができるゲーム機は他にもいくつかありますが、この2機種を押さえておけば、まず間違いありません。
どちらのゲーム機も専用のカードを読み込ませてプレーすることで、ブルに命中した回数や アワードの累計など、個人の成績を記録し手軽に管理することができます。
アワードの累計など、個人の成績を記録し手軽に管理することができます。
「数値化できない目標は"実行できない"とイコール」
日産自動車を経営危機から救ったカリスマ経営者の言葉です。
突然、会社経営者の格言がでてきて驚かれた方もいらっしゃるかと思いますが、実は、会社経営も勉強もスポーツも、効率的、かつ効果的に成果をあげるためには共通することがあります。
それは、具体的な数値目標を設けることです。
そして、その目標を達成するためには、現在の自分の実力を 数値で知る 必要があります。
目標とは、自分の実力値と目標値のギャップを埋めることで達成されるからです。
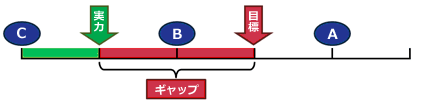
つまり、効率的、かつ効果的に上達するには、現在の実力値を数値で知るというプロセスが欠かせません。
好調やスランプなど常に変化を続ける実力値をプレーデータとして自動的に集計してくれるカードは、ダーツの上達に欠かせない重要なツールなわけです。
カードの重要性は概ねご理解いただけたと思いますが、ここで気をつけたいのは、ダーツライブとフェニックス、それぞれのカードには互換性がありません。
例えばの話、フェニックスのカードを持っていても、ダーツライブでは使えないということです。ただし、機種が同じであれば、例えば、ダーツライブとダーツライブ2はカードの互換性がありますから、どちらでも使うことができます。
ですから、まずはよく行くお店に置いてあるダーツマシン用のカードを購入するのがよいでしょう。
気になるお値段は、各500円となっており、ゲームできるお店で買えることが多いです。各カードは製造数が決まっていて人気のあるカードは未使用を条件にプレミア価格が付いたりもします。気に入ったデザインのカードを見つけたら即決してしまいましょう。
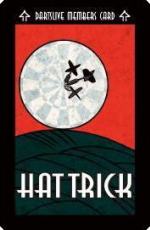
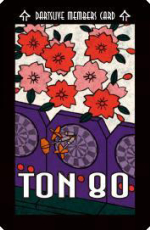
※人気のダーツライブカード『花札』シリーズ
上記以外にも、テーマ(プレイ画面の背景)やアワードの設定、グループ作成などのお楽しみ要素が満載です。
ダーツカードに名前を登録しよう
カードを購入したら、早速、名前(愛称)を登録しましょう。カードに名前をつけると愛着がわき、不思議と大切にできるものです。
そういえば、1998年〜1992年に週間少年ジャンプで連載された人気漫画『まじかる☆タルるートくん』に登場したヒロイン、河合伊代菜(かわいいよな)も消しゴムなど持ち物に名前をつけ、異常なほど大切にしていました。
名前の登録は、最初の一回だけでOKなので、プレーの都度登録しなおすような手間はありません。
もちろん、何度でも無料で編集できますからご安心ください。
登録(または編集)方法はいくつかあります。
1.ダーツマシンで登録する。
名前の編集ができない機種もあります。例えば、ダーツライブでは登録可能ですが、ダーツライブ2では登録できません。使える文字の種類に制限があることにも注意が必要です。
2.タッチライブで登録する。
ダーツライブカードの場合はタッチライブというゲーム機でも登録できます。ただし、使える文字が限られています。
3.携帯電話やPCで登録する。
携帯電話やPCを利用し会員登録することで、文字の種類に制限なく登録できます。これが一番おすすめです。
 ダーツライブの会員登録 |  フェニックスの会員登録 |
ゲームしてみる
当然、ゲームをしないと成績が記録されませんから、実力を把握することもできません。
カードを読み込ませた状態でゲームをすると、カードに自分の成績が記録されます。ここでいう成績とは、特定ゲームにおける過去一定の平均得点や アワードの累計等を示します。
アワードの累計等を示します。
これらの成績は数字で定量的に確認することができるため、自分の実力を把握し易く、目標値を設定し練習に励めば上達に大きく貢献することは間違いないでしょう。
なかでも、01(ゼロワン)やスタンダード・クリケットを一定回数対戦することで付与される FLIGHTと呼ばれるクラス(C、CC、B、BB、A、AA等の階級)を把握することが自分の実力値を知る上で最も重要となります。
FLIGHTと呼ばれるクラス(C、CC、B、BB、A、AA等の階級)を把握することが自分の実力値を知る上で最も重要となります。
01(ゼロワン)やスタンダード・クリケットにおける過去の成績は、ある程度の回数(30回と言われています)対戦をすると消えていくので、最初がダメダメでも心配いりません。センスがよければカードもみるみる成長していきます。「そこそこ上手くなってから・・・」などと見栄をはらず、是非とも上達の仮定を楽しんでほしいと思います。
FLIGHT(レーティング含む)は対人戦をしないと変動しません。対人戦とは、直接的な対戦は勿論、通信対戦も含みます。一人で練習したりコンピュータと対戦しても変動しませんので注意が必要です。 |
FLIGHTは、その人の技術力を評価したもので、各社が模様すイベント等に参加する際も利用されることがあります。まずは、自分の成績を確認し、現状の実力値を把握します。
目標はAフラ
目を疑わないでください。目標はAフラです。
おって、中級者編で解説しますが、これは長期目標です。長期的なものなので中々イメージが浮かばない方もいるかとは思いますが、"目標"は"夢"と違い漠然とし曖昧なものではありません。
もちろん、これは初心者にとって決して低い目標ではありませんが、同時に達成できない目標ではありません。
マイダーツのすすめ
ほとんどのお店は、ダーツ(ハウスダーツ)が無料レンタルできます。
 |
ですが、ハウスダーツはシャフトやフライトが曲がっていることもあり、上級者が投げても思うようにコントロールできないことがあります。
つまり、技術が上達しても、使うもの(ダーツ)の品質が悪ければ、高い成績や安定した成績は残せません。
ダーツに少しでも魅力を感じたのならマイダーツの購入を強くオススメします。効率よく上達したければ尚のことです。
マイダーツは、フライトやシャフト、チップを代表とした各種消耗パーツを低コスト(数百円程度)で交換することができるので、ハウスダーツと異なり一定の形状を保つことができます。
また、パーツをカスタマイズすることで、より自分好みのダーツに仕上げることができます。マイダーツに対する愛着心も生じることでしょう。
素材にレアメタルが利用された人気のダーツでも1セット、3,000円程度から買えます。更に、自分好みにカスタムしても+1,000〜1,500円程度とお財布にも優しく安心です。
初心者にオススメのダーツ
オススメは、レアメタル(希少金属)の一つであるタングステンという素材でつくられたダーツです。
ダーツの素材は、 ブラスと
ブラスと タングステンが主流で、少し大袈裟ないい回しとなりますが、後者であるタングステンの方が高級品です。タングステンは金属の中でも密度が高い為、重くて硬い特性があります。ですから、ブラスと比較し同じ重さでバレルを細く加工できます。単純に考えると、ダーツが細い方が小さなターゲット、例えば、ブルに3本入り易いわけです。
タングステンが主流で、少し大袈裟ないい回しとなりますが、後者であるタングステンの方が高級品です。タングステンは金属の中でも密度が高い為、重くて硬い特性があります。ですから、ブラスと比較し同じ重さでバレルを細く加工できます。単純に考えると、ダーツが細い方が小さなターゲット、例えば、ブルに3本入り易いわけです。
全てのタングステン製ダーツが全てのブラス製ダーツより細いわけではありませんので、あしからず。
さて、もちろん、タングステンダーツにも沢山の種類があり、どれでも良いわけではありません。
オススメは、80%タングステンのHarrows Assassin 18gR(定価3,200円)です。初心者にも安心の前重心構造で飛行中にブレにくく、刻みの幅が広いため、どんな持ち方でも指にフィットし易いのが特徴です。
バレル、アルミシャフト、フライトが各3つ。チップについては予備を含め6つ。おまけに黒くて細いプラスチック製の簡易ケースまで付いてきます。
ところで、みなさんは店頭よりネットショップの方が、送料を換算しても断然お得なことをご存知ですか?格安のタングステンダーツ情報は下記リンクから。
太くて握り易いとか、単純に安いという理由でブラスダーツをすすめるサイトも少なくありませんが、太さの問題は慣れることですぐ解決しますし、値段もそれ程変わりません。それに、ブラスを買っても、すぐ上位となるタングステンが欲しくなります。逆にタングステンを先に買い、後から下位であるブラスが欲しくなる人はいないでしょう。 |
少しだけ補足をすると、購入時、Assassinに付属してくるHarrowsのチップは弱く折れやすいので、先を見越して買い足しておいた方がよいでしょう。予算に余裕があれば予備のシャフトも1セット欲しいところです。
ちなみに、チップのオススメはリップポイントのブラックかスノー(ホワイトではないので注意)。シャフトはナイロン製であればメーカや色を問いません。
下記の記事にあるオススメのカスタムも参考にしてください。
購入時の注意点
お店でダーツを探す際は、4点注意して下さい。
1つめ。同じダーツ名でも、いろいろなタイプがあります。(例えば、Assassinは6種類もあり、それぞれ形が異なります)
2つめ。同じダーツでもグラムが違うものもあります。(例えば、Assassinには16g、17g、18g、20gの4種類あります)標準は総重量18gだと覚えておいて下さい。バレルのみの重量とは異なります。
3つめ。できれば、試し投げできるお店へ出向き、何度か投げさせてもらいましょう。
最後に4つめ。ダーツを購入する際は、交換周期の早い消耗品であるシャフトやフライトのデザインで決めない事。バレルだけに着目して下さい。
分からないことがあれば、店員さんに聞きましょう。
オススメのカスタム
フライト
最初は安定性が高く飛び易いスタンダードタイプのフライトを使いましょう。ダーツを購入した時に添付されてくるフライトがスタンダードタイプでない場合は別途購入することをオススメします。
また、フライトはダーツの軌道を目で追えるよう明るい色にしましょう。ダーツ場は暗いところが多い為、黒や、暗色はオススメできません。
それから、勿体無いと思うかもしれませんがフライトの穴あけ(スロットロック)加工をしましょう。フライトに穴をあけ、リングでシャフトと固定することによりフライトが外れ難くなります。無料で穴あけ加工をしてくれるお店も沢山ありますので、まずは店員さんに問合せてみましょう。
>>..自分で穴あけ。小さくて高性能、手頃な価格のフライトパンチ
シャフト
Harrows に添付されるシャフトはミディアム(最長)です。正直、初期状態では全長が長過ぎると思うんです。テイクバックやリリースの際、違和感があれば是非インビトやショートを試して下さい。
シャフトはダーツの軌道を目で追えるよう明るい色にしましょう。ダーツ場は暗いところが多い為、黒や、暗色はオススメできません。
チップ
慣れないうちは、ダーツの飛びが安定しないためチップへのダメージがでかいです。ですから、最初はチップが折れ易いと思います。折れ難い丈夫なリップポイントのブラックかスノー(ホワイトではないので注意)を強くオススメします。
是非、パーツレビューも参考にして下さい。
ダーツの基本について
ダーツには万人に共通する投げ方の正解はありません。しかし、正解はなくても、基本はあります。
ここからは、ダーツの基本について紹介、解説します。
左目?右目?利き目を確認しよう
箸(はし)を持ったり、字を書く手を『利き手』と呼びますが、目にも同様に『利き目』というものがあります。
自分の利き目は簡単にチェックできます。遠くにあるものをしっかりと指差し、そのまま片目ずつ瞑ってください。どちらかの目は焦点があい、もう片方の目は焦点が大きく外れるはずです。
ダーツは精密なスポーツですから、狙い通りに投げ込むには、自分がどちらの目で照準を捉えているかを意識する必要があります。
スタンスを決めるさいは、利き目で無理なく照準を捉えられる姿勢を決めることが大切です。
スタンスを決めよう
 スタンスには大きく分けて、クローズ、ミドル、オープンの三種類があります。それぞれ、特徴がありますので、実際に構えてみてダーツが投げ易いスタンスを選ぶのがよいでしょう。
スタンスには大きく分けて、クローズ、ミドル、オープンの三種類があります。それぞれ、特徴がありますので、実際に構えてみてダーツが投げ易いスタンスを選ぶのがよいでしょう。

ダーツを投げる手と同じ側の足を前に出します。上記は右手でダーツを投げる人向けにつくったイメージです。
<左手で投げる方>
上記は左手でダーツを投げる人向けにつくったイメージです。
重心は、9:1か8:2を意識してください。前足にしっかりと体重をのせ、前方に少し体を倒します。後ろ足は添える程度で、ほとんど体重をかけません。
また、スローイングラインは超えないことがルールです。上記イメージのように、ガッツリ踏んで構いません。
スローイングラインに対し、前足を垂直に構えるのがオープンスタンスです。フロントスタンスともいいます。立ちやすくダーツボードも見やすいですが、目→ダーツ→照準を直線上に構えたあとで真直ぐテイクバックするのが難しいため、採用するプレイヤーは多くありません。
スローイングラインに対し、前足が45度程度になるような構えをミドルスタンスといいます。最も多くのプレイヤーが採用している主流スタンスですが、毎回同じ角度で立つのが非常に難しいというリスクもあります。
オープンスタンスとは逆で前足をスローイングラインと平行に構えることで、最も照準に近づいて投げることができるのがクローズスタンスです。サイドスタンスともいいます。体をひねる必要があるため、姿勢が窮屈になるリスクがあります。利き目と利き手が異なる人は腰に負担がかかりますからオススメできません。
構えたとき前にくる足(利き足)の角度が基準となりますから、例えば前足が垂直であれば後ろ足がどのような位置にあろうとオープンスタンスといえます。
ダーツの重心を知ろう
ダーツは重心をグリップするのが基本です。
では、ダーツの重心をどのように確認すればよいでしょう。
まず、ダーツをヤジロベイのようにして人差し指の上へのせましょう。安定したポイントが重心となります。
グリップを決めよう
人それぞれ、手の形は異なりますから、身近にいる上手な人や、雑誌に紹介されたプロのグリップをマネても上手く投げられるとは限りません。それらは、参考に留め自分流にアレンジするのがよいでしょう。
一つ、共通してアドバイスできることがあるとしたら、グリップは、"ニギル"というより、やさしく"ササエル"イメージであるということです。
また、注意点として、上手く投げられないからといってコロコロとグリップを変えることは好ましくありません。
ブルに向かって投げよう
「人生の偉大なる目的は知識ではなく行動である」
ダーウィンの進化論を弁護し<ダーウィンの番犬>と呼ばれた偉大な研究者、トーマス・ハックスレー氏の言葉です。
ここまで初心者として基礎を学んだ目的は"上達するため"であり、"知識をつけるため"ではありません。読んだだけで決して満足しないでください。
あとは、目標に向かって投げます。足や腰、肩を使わず、肘(ひじ)を支点に腕だけを使って投げます。そうです。投げて、投げて、投げまくるのです。
初めは、ダーツに必要な筋肉が足らないので、手を振る動作を維持するために体の重心などを動かすことで無意識にバランスをとってしまうものです。
しかし、ダーツをうまく飛ばすには重心を動すなど、とにかく土台である体が無駄に動いてはいけません。
投げる動作に慣れ、つまり筋肉が養われてくると1〜2時間投げ続けても動じなくなります。まずは、このレベルに達するまで楽しみながら投げ込みましょう。
ブルに入らなくても決して焦ることはありません。
この初心者編では、〜CCフライト程度を想定していますが、Bフライト程度であればここまでの情報を気に留めて練習することで十分達成できます。
こんなイメージを頭の片隅に
無駄に体が動かないよう、最低でも前足は伸ばしきる。
利き手でない側の腕はかるく脇をしめて体の重心を安定させる。
肘(ひじ)から先だけを稼動し投げるイメージをつかむ。
できれば、一定のリズムで投げること(構えてから1、2、3で投げるとか)と、ブルに入ったときなど上手くいった感覚を体で覚えることも意識する。
狙いすぎない。力まない。上手な人は緩やかなスローイングで綺麗にダーツが飛びます。
練習中は適度に休憩をし、上手そうな人のフォームを観察する。
最後に、ダーツがマトに届かなくても泣かない。
>>..初心者の具体的な練習法
上下左右の狙い方
ブルばかりをストイックに狙い続ける練習もよいですが、たまにはクリケットやパーティゲームなど気晴らしに手を出してみましょう。
はじめの頃は特に、投げ込むことで基本的な筋肉を養うことが大切です。できれば、楽しみながら鍛えたいものです。
ここでは、ブルを支点に、上下左右への照準(狙い)の定め方を簡単に解説します。
効率的に上達するための基本方針は、「どこを狙っても同じフォームで投げられること」です。
この基本方針に基づくと、上下左右共に"腰"で調整することが理想といえます。
ロボットダンスのイメージで、腰以外の部位は動かしません。基本的なフォームを崩さないことが大切です。
逆に、照準の調整ポイントを肘(ヒジ)などの可動部にしてしまうと、「どこを狙っても同じフォームで投げられること」の基本方針に支障をきたします。
上下を肩や肘(ひじ)、リリースポイントなど他の方法でで調整するプロプレイヤーもいまが、この方法は、投げ方が増える分、練習量が多くなります。
>>..初心者の具体的な練習法
ゲーム中の心得
ダーツ場は暗いところが多く、置き引きが多いようです。会社の資料が入ったカバンでも盗まれれば大変なことになりますから、特に一人で練習するときは、カバンや貴重品等をダーツマシーンの前や横に置くよう心掛けましょう。両替等、席を外すときは面倒でも持ち歩くことです。
情報漏洩だのコンプライアンスだの、正直聞くだけで耳が痛いです。
ちょこっと補足。 |
| [基礎編] [初心者編] [中級者編] [上級者編] [FAQ] [トップページ] [初心者の練習法] [中級者の練習法] |
| ネットでダーツ代を稼ぎませんか? |
|
せめて、ダーツ代くらいネットで稼いでみませんか?アフィリエイトは、ネット環境と報酬の振込先(銀行口座等)、それと根気さえあれば先行投資なく収入を得ることができます。 |
| スポンサードリンク |